遠洋マグロ漁船に乗った10年の物語
諍いの海
船が港から外洋に出ると船は揺れだした。
マグロ船特有のローリング&ピッチングだ。
まさる君はその揺れに逆らいながら、他の船員とは逆方向に体重移動をし船の揺れに抵抗しているように見えた。
「ありゃ30分もすると気持ち悪くなるな」と僕は思った。
しかし、それを教えても理解できるものではない。
体が無意識に反応し、頭で理解できても体は言うことを聞かない。
一年前の僕もそうだった。
片付けが終わると、船頭が僕を呼びとめた。
「この航海だけお前が飯炊きしろ、まさるがマグロ船が続くようだったら次の航海から飯炊きをさせる」と僕に言った。
それは想定していたので、別に驚きもしなかった。
その航海は、総員8人での出港で、時計を見ると16時前だった。
僕の当直は飯炊き専用固定ワッチ(当直)の18~20時で、ワッチまではまだ時間がある。
今寝てしまうと、夜眠れなと思いワッチの時間まで寝台に設置されたTVでビデオを観た。
ビデオは最高だ!
出港した当日の夕食は幕の内弁当なので、夕食の用意をする必要はない。
17時30分、僕は弁当を食べてから当直に行こうと寝台を出て船員室から食堂に出た。
その時、テーブルの上の弁当を確認すると、弁当は4個残っていた。
幕の内弁当を食べて、ブリッジ行きワッチについた。
ワッチが終わり、寝台に戻ろうと船尾の船員室に向かった。
船員室に入る時、テーブルの上には弁当が一つだけ残っていた。
それが、まさる君の弁当だと言うことは明らかだった。
翌朝、朝食を作ろうと6時に起きて船員食堂に出てみると、その弁当はまだテーブルの上にあった。
船員達が朝食を済ませ仕事の準備に入り、僕も朝食を済ませ朝食片づけをして昼食の準備をし仕事に加わった。
仕事に加わると、あれ?一人足りないんじゃない?と思った。
まさる君の姿が見えない。
怪物君に「まさるが出てきてないよね?起してこようか?」と言うと、それを聞いていたボースンが「寝かしとけ」と僕に向かって言った。
へ!?寝かしとけ!?
僕、髪を鷲掴みにされて寝台から引きずりだされましたよね??
驚いたような顔でボースンを見てると、ボースンは僕に向かって言った。
「どうせ“お客さん”だろ、無理させんな」
当時マグロ漁船には、一攫千金に憧れて乗船してくる人は少なくなかった。
しかし、そういうロマンな人は大体1航海でマグロ船を辞めていく。
船員達は、そういう人のことを揶揄し“お客さん“と呼んだ。
「お客さんなら、仕方ないね」と僕は言って、怪物君と談笑しながら仕事を続けた。
出港して4日目の朝。
いつものように賄いの片付け後作業に加わると、顔面蒼白で頬のコケたまさる君がいた。
僕はまさる君に「大丈夫?」と声を掛けた。
まさる君は「大丈夫、もう慣れたから」と答えた。
しかし、その顔面は青白くで血の気が全く、全然大丈夫そうに見えなかった。
正午、仕事が終了し僕は用事を済ませて賄いの片付けようと食堂に行った。
テーブルの上には、昼食のチャーハンが二皿残っていた。
一つは僕ので、もう一つは多分まさる君のだろう。
僕はまさる君の寝台に行きカーテンを開け「まさる君、ご飯食べたの?」と聞いた。
まさる君は、寝台の電灯を付けて「気持ち悪くて食べれない」と答えた。
僕は「気持ち悪いのはわかるけど、食わなきゃずっと気持ち悪いままだよ」と言った。
するとまさる君は「あとで食べるから」と怪訝そうな顔で言った。
「後で食べるじゃねーよ。あんたが食べねぇと俺の片付けが終わらねぇんだ。いいから黙って騙されたと思って食べてみなよ」と言い、続けて「俺もあんたと同じ思いしたんだからさ。食べて吐いてみなよ、大分楽になるから」と言うと、まさる君は顔を上げ「わかった」と言って起き上がり、僕と一緒に昼食をとった。
まさる君はチャーハンを二口食べてウッとなり、船尾甲板に続く階段を駆け上がって外に出て行った。
数分して戻ってきて、そのまま船員室に入ろうとしたので「ちょっと待て!もう一回食べて、今のもう一回やってみな」と、僕が言うとまさる君は「無理」と答えて部屋に戻ろうとした。
「無理じゃねぇ!黙って言うこと聞け!食べろ!!」と僕が声を荒げると、まさる君はムッとした顔で腰をおろしチャーハンを食べは始めた。
「全部食べろよ。食べなかったらブン殴るぞ」と言って、僕は船員室に入り寝室に横になった。
すると寝台の下からパン!パン!パン!と音が聞こえる。
下の寝台の電灯が付いていて、カーテン越しにシルエットが映し出されている。
怪物君だ。
僕は怪物君の寝台のカーテンを開けて「またやっての!?」と聞くと「ばかやろ~!爪で背中ガリッだぞ!」といつもの返事。
「背中に爪の跡ついてるの見たことねーぞ!」と突っ込むと
「ばかやろ~!!俺は一日で治るんだよ!!」と、平気な顔をしてウソをついた。
「強めにバシバシやんないと、背中ガリッて無理なんじゃない?」と煽ると、怪物君は渾身の力を込めて濡れタオルを自分のイチモツに振り下ろした。
バシッ!!!と、とても良い音がした瞬間、怪物君の顔がゆがんだ。
「あれ?痛いの?今、痛かったんでしょ!?」
「ばかやろー!痛くねぇよ!!ばかやろー!」と引きつった笑顔の怪物君。
それ以来、怪物君は僕の目の前でバシバシバシをしなくなった。
翌日、まさる君の顔色は元に戻っていた。
僕を見かけたまさる君は「いやーー船酔いって結構キツイんだなぁ!!」と、デカイ声で言った。
仕事中、まさる君は大きな声で話し続けていた。
「僕、自衛隊にいたんですよ!相当鍛えたから、船酔いさえ治れば大丈夫!」と、“元自衛隊”を、強調していた。
出港して12日目、船は第1回目操業をむかえた。
1回目操業の揚縄が終わり、まさる君を見た。
あきらかに、疲れたきった顔をしていた。
2回目操業の揚縄の時、まさる君は魚倉の上に座り込み動こうとしない。
「商売!!」
縄先から声がした。
僕は、枝縄を受け取った。
その頃には僕は、枝縄を持った感覚で何が釣れているのかわかるようになっていた。
「サメだ」と僕が言うと、怪物君が鉤(カギ)を構えた。
船にサメが上げられ、生きていて暴れている。
「おい、サメ殺せ!」と、まさる君は先輩に言われた。
すると、まさる君は面倒臭いと言わんばかりの明からに嫌な顔をした。
その、面倒臭そうにしているまさる君の顔を見たある先輩が、まさる君をドヤしつけた。
「てめぇ!なんだその顔は!なんか文句でもあんのか!」と。
まさる君は「文句なんかねーよ!」と、先輩に対して怒鳴り返した。
当たり前のことだが、怒られると誰でも嫌な気持ちになる。
まさる君にとっては、全てが初めての経験で疲れもストレスも相当溜まっていたんだろう。
何かに怒りを打つけなければ、自分が壊れてしまいそうなる感覚はわかる気がした。
僕も経験したことだ。
そんな時、ボースンに言われた。
「怒る元気があるんだったら、もっと働け。動け。」
その言葉で、冷静になれた。
ボースンの言っていることは正しかった。
しかしその時、まさる君は完全に自分を見失っていて混乱していて、怒鳴りつけた先輩に殴りかかって行った。
まさる君の身長は180㎝を超え、元自衛隊と言うことは多少の格闘技の経験もあっただろう。
先輩船員との身長差はかなりあった。
二人は取っ組み合いの喧嘩を始めた。
前にも書いたが、船には病院は無いし医療従事者もいない。
小さな怪我が死に繋がることが多々ある。
ラインホーラーが止まり、揚縄は一時中断した。
二人を止めなければ。
僕はまさる君の着ているカッパの後ろを右手で持ち、それを力の限り引っ張った。
まさる君は、僕の足元に転がった。
まさる君はビックリした目で僕を見ながら「お前、何するんだ!」と叫び、僕に向かって来ようとした。
キックボクシング経験者の僕は、真っ直ぐ向かってくるまさる君を受け流し、左ミドルキックをまさる君の右脇腹に決めた。

ドスッ!
左ミドルキックは綺麗にまさる君の右脇腹の決まり、まさる君は腹を抑えて甲板にうずくまった。
僕はうずくまるまさる君に向かってマグロ解剖用の包丁を投げつけ、僕も右手に包丁を持った。

「その包丁持て、俺にかかってこい。子供の喧嘩じゃねぇんだ、大人の喧嘩をやろうじゃねぇか」
そう言って、まさる君を睨みつけた。
まさる君は唖然とした顔で、僕を見上げていた。
誰も何も言わないし、止めようともしない。
甲板は静寂に包まれていた。
みんなは、僕が何をしたいのかを理解していた。
まさる君は包丁を持つことなく、うつむいた。
僕は、まさる君に近づき
「ここは船の上なんだ、舐めたことすんじゃねぇ。病院も無いし医者も居ねぇんだ。ちょっとでも誰かに怪我させてみろ、間違えたらテメェ人殺しになんだぞ。人殺しになる覚悟がねぇなら、なめたことすんな」と言った。
僕は手に持った包丁を置き「どうせ疲れるんなら、気持ちよく疲れた方が良くねえか?」と、まさる君に言った。
まさる君は反省した顔で「はい」と言って立ちあがり、さっき揉めた先輩ところに行き「すみませんでした」と謝罪をした。
先輩は「わかった。俺も怒鳴って悪かったな」と言った。
揚げ縄が再開された。
無力の海
その出来事も操業の回数を重ねる日々の中で忘れられていった、11回目の揚縄の時だった。
上原さんという、先輩がいた。
年齢は当時38歳。
今の僕より、若い事になる。
色黒で背が高くガッシリした体系で、優しい海の男で結婚はしていなかった。
僕が初めて乗った時から、一年以上苦楽を共にしてきた仲間だ。
上原さんは優しい人で、寡黙で声を荒げることも怒ることも無かった。
僕がボースンや船頭に怒られた時「あれだけ殴られたら、誰でも弱音吐くのに。お前は一切弱音を吐かない、大したもんだ」とか「初めてマグロ船に乗ったとは思えないな!お前、即戦力だ。」と、新人の僕をただ一人褒めてくれ励ましてくれた。
そんな上原さんは大酒飲みだった。
酒を飲んで酔っ払って暴れたりすることは無く、酔いに揺られているのが好きな人だった。
とにかく酒が大好きで、まるでコーヒー飲むかのように大きめのマグカップに並々とウィスキーを注ぎ、キューっと半分近く一気に飲み、その後はチビチビと飲むのが好きだった。
漁師に酒飲みは多いが、あれほどの酒好きは今まで見た事が無い。
よく船頭に「お前、飲み過ぎだぞ。体壊すぞ」と説教をされていた。
投縄が終わって、友船(ともぶね)と会合をした。
友船とは、仲間の船という意味で、一般的には“僚船(りょうせん)”と呼ぶ。
会合とは、船同士が物々交換をすることをいう。
その日の会合でスイカを貰った。
揚縄中、僕は夕食を済ませて夜食の支度をし夕食のデザートにと思い、会合で交換したスイカを切り分けて揚縄に持っていった。
その日は無風状態で、投光器に照らされている甲板の気温はとても高かった。
揚縄を続けながら、船員は交代で休憩をとりスイカを食べた。
上原さんも船員達と一緒に談笑しながら、スイカをおいしそうに食べていた。
揚縄は順調に進み、上原さんは船尾の倉庫に枝縄が収められたカゴやウキを片付けに行った。
上原さんが船尾のベルトコンベアーのボタンを押したのだろう、船首甲板のベルトコンベアーが回りだし載せられたカゴとウキが船尾に送られて行った。
ベルトコンベヤーが止まった。
僕は、いつものように揚縄に参加しブランリールで枝くりをしていた。
上原さんが船尾に行ってから數十分が経った頃、船頭が窓から顔を出してまさる君に声をかけた。
「おい!上原が甲板に戻ってないぞ。まさる、見て来い」
まさる君は、甲板からブリッジの横の階段を上がり船尾に駆け足で行った。
少しして、まさる君が血相を変えて甲板に戻って来て「上原さんが倒れてます!!」と叫んだ。
縄を巻き上げるラインホーラーが止まり、船が停止した。
船頭がブリッジから飛び出し、船尾に急いで行くのが見えた。
船頭に続き、僕や船員達もそれに続いた。
船尾に行くと上原さんが船尾の床に仰向けに倒れていて、目は半開きになっていて口からは白い泡のような物が流れているのが見えた。

その姿を見た時「マズい」と思った。
学生時代、救急救命の講習を受けたことがある。
人は病気が原因で倒れる時前のめりに倒れる、人間の骨格は前方にしか曲がらないからだ。
しかし後ろ側、すなわち仰向けに倒れた場合、倒れた人は無意識のうちに倒れた可能性が高く、その場合、生命に関わる疾患の可能性が高いと教わったことがあった。
顔色を見ると、上原さんの黒い顔は青みかかっていてどす黒く見えた。
船頭が「上原!」と声を掛けたが、上原さんは全く反応しなかった。
船頭は、上原さんの頬っぺを何度か叩いが全く反応がなかった。
船頭が「俺は無線で陸の緊急連絡をする!ケイジ!救命措置しろ!」と僕に言い、ブリッジに駆けて行った。
僕は手袋を取り、上原さんの口と鼻のところに手を当てて呼吸の確認をした。
呼吸は確認できなかった。
次に上原さんの胸に耳を当て、心臓の音を聞いた。
しかし、エンジン音が上原さんの体から伝わってきて、心臓の音も鼓動も確認ができない。
脈拍を確認しようとしたが、やはりエンジンの振動が上原さんの首や手首から伝わって来て確認ができない。
機関長に「主機エンジンを止めてもらえますか?心臓の音が聞こえないんです。」と言った。
機関長は頷き、機関室に走った。
まさる君に「懐中電灯を持ってこい」と言うと、まさる君はブリッジに走って行き懐中電灯を持って来た。
僕は懐中電灯を使い、上原さんの閉じている目を明けて瞳孔を確認した。
上原さんの瞳は白く濁っていて、懐中電灯の光を当てても瞳の中心が動くことは無く、瞳孔は開いているようだった。
主機エンジンが止まり、船の振動は無くなった。
僕はまた、上原さんの胸に耳を当て鼓動を確認したが鼓動は聞こえなかった。
「誰か、上原さんのカッパと上着を脱がせて!」と僕が言うと、兄が上原さんの履いているカッパと上着を脱がせた。
僕は、人工呼吸用のマウスピースをブリッジに取りに走った。
ブリッジに行くと、船頭が日本船舶医師会への緊急無線連絡を繰り返していた。
救命道具箱から人工呼吸用のマウスピースを取り出し、操舵席のクッションを持って船尾に戻った。
僕は上原さんの気道を確保しようと、クッションを丸めて上原さんの後頭部の首の付け根にクッションを入れ、顎を押して口を開けてマウスピースを口に差し込こんだ。
兄に「ここの部分を力一杯、強く押してくれ」と言い、心臓マッサージのやり方を教えた。
僕はマウスピースに口にあて息を吸い込みマウスピース伝いに息を吹き込んだ。
僕が息を吹き込むと、上原さんの肺が膨らんだ。
マウスピースから口を離すと、膨らんだ肺が萎むと共に口からは空気が漏れた。
上原さんから漏れてくる空気には、全く意思が無かった。
兄に「力一杯押して」と言い、ボースンに「耳元で、声をかけてやってくれ」と言った。
ボースンは上原さんの耳元で「上原!」と何度も声をかけた。
それを、何度も何度も繰り返した。
数十分して、船頭がブリッジから船尾に来て「どうだ!?」と聞いた。
救命措置を始めてから、どのくらい時間が経ったのか全くわからなかった。
僕が「意識がありません」と言うと、船頭は「続けろ」と言ってまたブリッジに戻って行った。
僕は人工呼吸を繰り返し続けてた。
僕の顔から上原さんの顔に、僕の汗が落ちた。
上原さんの顔に落ちた汗は、人間の顔の皮膚の上に落ちた感じではなかった。
まるで、無機質の物体に落ちたかのようだった。
それは、人間とは違う全く意思をもたない物体に思えた。
それを見た時、心の中で「死んだ?」と思ったが、声には出さなかった。
それから30分位経った頃、船頭が再度船尾に来て、改めて「どうだ?」と僕に聞いた。
僕は、かぶりを振るしか出来なかった。
船頭は「替われ」と僕に言って、上原さんの横に屈むと上原さんの半開きの目を指で開き瞳孔を確認した。
次に手で呼吸を確認し、胸に耳を当てて心臓の音を聞いた。
そして「ダメかもな」と、ポツリと言った。
ついさっきまで、一緒に仕事をして、スイカを食べ、笑ってた人が突然亡くなった?
僕は「夢だろ?」と思った。
「そんな簡単に人が死ぬ訳ないよ、さっきまで元気だったんだ。嘘だろ?」
僕は心の整理が付かずに、その言葉を繰り返し頭の中で連呼していた。
マグロ船に乗って約1年が過ぎた。
毎航海、大小はあるが誰かが何かしらの怪我をした。
しかし、これまで事なきを得て来た。
みんな、怪我の大小に関わらず“生きていた”いた。
だがそれは、もしかしすると生と死の間のスレスレのラインを歩いていただけかもしれない。
しかし、どんなにスレスレであろうと、結局は必ず生の方に歩み最後には笑って話せる日が来る。
そう信じていた。
それまで、他船で怪我や病気が原因で船員が亡くなる事故の話を何度か聞いたことがあった。
自分の乗っている船ではなかったため、話を聞いても実感もなく、全く他人事だった。
まるで、自分は安全な場所居て、遠い雷を聞いているかのように。
遠雷を聞くが如く、自分は安全な場所にいると思い込んでいた。
そしてこうも思っていた「俺の乗った船は何があろうと大丈夫さ、絶対に誰も死にはしない」
本気で、そう思い込んでいた。
しかし本当は、死はすぐ側にあり僕たちは常にその危険性に晒されていただけだった。
そして僕たちは、人を助ける術も方法も持ち合わせていないことを知らしめられた。
横たえている上原さんを見ながら、心の中で絶望感と恐怖心とが交差した。
呆然となる船員達に船頭が「上原をブリッジに運べ、とにかく縄をあげよう」と声をかけた。
あまりにも突然すぎて、悲しむ余裕も無かった。
怪物君が「ケイジ、上原さんの肩の方を持ち上げろ。俺が足を持つから」と僕に言った。
持ち上げた上原さんの体は、すでに死後硬直が始まっていた。
それは、感覚でわかった。
上原さんをブリッジに運んだが、ブリッジのドアは小さいため一度入れると二度と出せなくなると思った。
僕が船頭にそれを言うと「そうだな。毛布を敷いて機関室の通路に横にしといてやれ」と言った。
ブリッジの後方には、甲板通路から機関室入り口につながる通路がある。
その通路に上原さんを運び、毛布を敷いてその上に横たえた。
怪物君が、タオルで上原さんの顔を覆うようにとタオルを持ってきが、僕はそれを止めた。
怪物君は、黙ってうなずいた。
ブリッジでは、船頭と機関長が話し合っていた。
揚縄が終わり、二番魚倉に入っているマグロ用の餌を全て海に捨てた。
空っぽになった二番魚倉に、上原さんを入れるように船頭から指示が出た。
腐敗をしないよう、上原さんの遺体を冷凍保存するのだ。
みんなで、二番魚倉に上原さんを運ぼうとした時、船頭が「上原の体を洗ってやれ」と言った。
僕と兄と怪物君は三人で、上原さんの体を洗った。
その時、僕の心は無だった。
何も考えられないし、何の感情も沸いてこない。
今思えば、無にするしか無かったのかもしれない。
仲間の突然の死を、受け入れることができなかったのだと思う。
体を洗い、遺体を二番魚倉に運び入れた。
その時、改めて呼吸と心臓の音を確認したが、はやり何も感じ取れなかった。
僕は、上原さんの大好きだったウィスキーを枕元に置き、船の揺れで転がらないようにロープで瓶を縛って固定した。
二番魚倉の扉は固く閉じられ、二度と開かないよう固く縛りつけられた。
揚縄が再開されたが、皆終始無言だった。
上げ縄が終わり風呂を終えた後、船頭にブリッジに来るように言われた。
ブリッジに行くと、兄と船頭がいた。
船頭が「母ちゃんが上原の家族に事情と状況を説明した。船首の魚倉が一杯になるまで、操業をして良いと許可をもらった」と、悲痛な顔で僕達に言った。
母は上原さんの家族に土下座をしてお願いしたと、帰ってから聞いた。
僕と兄は、その意味を良く理解していた。
前の2航海、水揚げ高は芳しくなかった。
マグロ船を経営する家に生まれ育った僕は、水揚げ高が家計を左右することを子供の頃から嫌という程思い知らされて育った。
少年の頃、母が金を羨む姿を見て心を痛めた事が何度かあった。
しかし、船の全権を持つ船頭が決めた方針だとしても非常事態である。
船員達の心の負担は相当なものだろう。
船員が働かなければ、操業は出来ない。
その日、寝台に入った僕は「なぜ、異常に気付いてやれなかったのか?」そればかりを考えて一睡もできなかった。
翌日、船は休みを取り、兄と二人で船員一人一人に事情を説明し操業を続ける許可を貰った。
まさる君以外の船員は快く引き受けてくれた。
まさる君は、無理もない。
初めて乗った航海で、人の死に直面したのだ。
あの光景を目の当たりにして、自分はああいう死に方はしたくないと思ったに違いない。
それ以来、まさる君は投縄も揚縄も拒絶し寝台から出てこなくなった。
翌日から、6人で休み無く操業をした。
一度だけ、まさる君の寝台に行き「なあ、仕事してくれよ」と言ったが、まさる君は僕に背を向けて「ごめんなさい」と言うだけだった。
操業15回で、上原さんの入っている二番魚倉を除き、船首の魚倉はいっぱいになり帰港を開始した。
その航海の帰港中は、どの航海よりも長く感じた。
船は、水揚げ地には寄港せず、直接郷里の港を目指した。
入港する前日、上原さんが眠る二番魚倉の冷凍を止めた。
その夜、遺体の確認をするため、船頭が二番魚倉に入って行った。
僕と兄が一緒に入ろうとすると「お前達は見なくていい」と言われたので、僕達は魚倉の入り口から魚倉の中を覗いていた。
魚倉には電灯が設置されていないため、船頭は小さな電灯を持って魚倉内に入り、その電灯の光で船頭の影が見えた。
少しすると、影は小刻みに揺れ「上原、帰ってきたぞ。ごめんな、ごめんな」と声が聞こえた。
翌朝5時過ぎの夜明けと共に、船は港に入港した。
船の甲板部分は青いビニールシートで覆われ、外部からの視覚を遮断していた。
岸壁に、上原さんのお姉さん夫婦と、母と祖父が来ていた。
船の隣に海上保安庁の巡視艇が繋がれ、海上保安員と検死官が乗り込んできた。
海上保安員から全船員下船許可が下りるまで、船から降りないようにと言われた。
上原さんの遺体を二番魚倉庫から出し、船首甲板に横たえると検死官による検死が始まった。
検死官は、遺体に外傷が無いかを念入りに確認した後胸の当たりを筒状の物体を刺して、心臓の一部を取り出し確認した後、事務的な口調で「精密検査では無いので確定では無いですが、おそらく心筋梗塞だと思われます」と告げた。
検死が終わると、陸から棺桶と白装束と清水(せいすい)が運び込まれた。
上原さんの体を清水で洗い、白装束を着せた。
船頭と僕と兄、それと上原さんのご遺族と一緒に、綺麗になった上原さんを棺桶に収め、上原さんの手に六文銭が書かれた紙を持たせ棺桶の蓋を閉じた。
上原さんの棺桶が陸に上げられている時、上原さんのお姉さんは泣きながら棺桶を撫で「お帰り」と言った。
共に笑いながら帰ってくるはずだった。
その光景を目の当たりにした船員達は、船友を亡くした悲しみと助けられなかった悔しさで打ちのめされ、堪えてきた気持ちが一気に噴き出し、皆その場にしゃがみこんで泣き崩れた。
出会いの海
次の航海に出るまで、船頭が海上保安庁の取調べなどを受ける必要があったため、船や約1ヶ月の休養を余儀なくされた。
休業の間、3人は他船に移っていった。
船乗りは験(げん)を担ぐ。
事故を起こしてしまった船は忌み嫌われ、なかなか船員が集まらない。
それが死亡事故ともなれば、尚更のことだ。
“板子一枚、地獄の底”
抗うことのできない大自然で、すがることも頼る場所もない大海原が職場。
何か事が起これば、残された者は祈るしか無い。
前時代的と言われるかもしれないが、愛する者達が危機に瀕している時、神にすがり祈るしかないのだ。
僕を含む、残った船員は4名。
59トン型のマグロはえ縄漁船で航海をするには、最低でも8人の船員が必要だ。
7人で出漁する船もあるが、船員1人に掛る負担は相当なものになる。
仲間の死に直面し、改めて命の尊さと儚さを思い知った。
しかし、悲しんでばかりはいられないことも事実だった。
漁に出ない漁師は、無職と同じだ。
それに前を向かなければ、生きて行けない。
船に船頭の兄弟で、僕の叔父である2人が乗船する事になった。
一人の叔父は船頭の兄で、すでに40歳を超えていた為、飯炊き専門として乗船した。
残りの船員は、外国人船員で補うことになった。
フィリピンからの、出稼ぎ船員である。
上原さんの四十九日法要を済ませ、フィリピン人船員を乗船させるためグァム島へ向けて航海に出た。
乗船てきたフィリピン人船員は2名。
一人は1航海で辞めたため、名前は覚えていない。
もう一人は、氏名:サスピノサ・レンドン、年齢:21歳、既婚。
彼が乗船してきた時、まず驚いたのは日本語が全くできなかったことだった。
「はい」や「いいえ」という、簡単な日本語さえ理解できなかった。
彼はフィリピンの母国語であるタガログ語と、第二母国語である英語を話した。
彼の話す英語は、フィリピン訛りが非常に強かった。
もちろん言葉のわからない外国人だからといえ、仕事が軽減されれるわけではないし仕事の厳しさが、変わるわけでもない。
レンドンは頭の回転が早く利口で、その場の空気が読める敏感さも持っていた。
怒られた時はなぜ怒られたのか?褒められた時はなぜ褒められたのか?を感覚で覚え、船内での日本人の生活様式に、一生懸命馴染もうとした。
そんな彼を、まだ若く幼稚だった僕はどこかバカにしていた。
言葉が理解できない彼らを、無視する事もあった。
日本語も喋れずに何故日本の船に乗るのかが、僕には全く理解できなかった。
レンドンが信仰している宗教はキリスト教でカトリックで、危険だと思った作業をする時、彼はいつも胸の前で十字を切る仕草をした。
そんな仕草を目の当たりにすると、僕に無い感覚だったので違和感を感じざるを得なかった。
操業が始まると、言葉の壁は顕著になった。
仕事を教えたくても、言葉が通じない。
日本人船員達にはそれがジレンマとなり、いつしかストレス変わっていった。
操業が進むにつれ、レンドン達は度々怒鳴らた。
言葉が通じないため、危険なことや間違ったことなどを怒ることでしか教えることができないのだ。
そんな時、もう一人は明らかに敵意ある表情で怒鳴った人を睨みつけるが、レンドンは不思議そうな目で観察するように相手を見ることが多かった。
そのレンドンの眼差しは、相手をバカにしているように僕には写った。
漁場を移動する「適水」の日。
眠っている僕を、兄が「ワッチ(当直)だ」と起こした。
そして「次のワッチはどっちかのフィリピン人を起こせよ」と僕に言った。
僕はワッチが終わった後、レンドンの寝台に行き彼を起こした。
ワッチ交代の時は、次のワッチがブリッジにくるまで前の船員はブリッジを離れることはできない。
僕は、レンドンが交代に来るのを待った。
彼はブリッジに入って来て「コウタイ!(交代)」と言って、僕に白い歯を見せて笑った。
少し日本語を覚えたようだ。
僕はポータブルCDプレイヤーとCDを持ち、操舵席をレンドンに譲ろうと立ち上がると、レンドンは僕の持っているポータブルCDプレイヤーとCDを興味津々に見ていた。
「ん?これ知ってるのか?」と、僕はCDを見せながら日本語で聞いた。
すると「BON JOVI サイコウ!」と、彼は言った。
僕は「聞くか?」と日本語で言い、レンドンにCDプレイヤーを差し出した。
彼は、ポータブルCDプレイヤーを初めて見たようだった。
ポータブルCDプレイヤーをレンドンに手渡すと、それをマジマジと見ながら「Small」とつぶやいた。
彼はヘッドフォンを耳に当て、プレイボタンを押した。
ヘッドフォンからBON JOVIの「Livin’OnAPrayer」の音が漏れた。
 | 【送料無料】 Bon Jovi ボン ジョヴィ / Greatest Hits – The Ultimate Collection (2CD) 【CD】 価格:3,663円 |
ヘッドフォンをしているからだろう、普段より大きな声で「サイコウ!!!」と笑って言った。
彼はワッチをする操舵席に座り、体を揺らしながらリズムを取り踊るような仕草をしていた。
その様子が可笑しかった僕は、彼を見て笑った。
笑っている僕を見たレンドンは、僕の笑顔を見て笑った。
僕は寝台に戻り、ビデオを見ていた。
2時間が過ぎた頃、レンドンがCDプレイヤーを返しに僕の寝台にやってきた。
プレイヤーを僕に渡し「アリガトウ」と言った。
それ以来、僕はレンドンを観察するようになり、僕は僕なりに彼を理解しようとし始めていた。
そんな時、ある事に気がついた。
彼は、一度怒られた事は二度としない。
そして、彼が怒られたときに見せる相手を観察するような眼差しは、何に対して怒られたのか?を理解しようとしていることに気がついた。
言葉がわからなくても、相手の表情や表現である程度相手の感情は理解できる。
彼は、相手の表情や表現の変化を観察することで、やっても良い事なのか悪い事なのかを理解しようとしていた。
操業が10回を過ぎた頃、物覚えが良い彼はサメの殺し方も結構サマになりはじめていた。
生きたサメが上がると、僕は親指を立て喉を搔き切る仕草を彼にした。
“殺せ”の合図だ。
レンドンに合図をすると、レンドンは躊躇なくサメを殺した。
彼が日本語を理解できれば、どれだけ早く仕事を覚えることだろうとつくづく思った。
操業が最終回を迎える頃には、どこか漁師の風貌さえ漂うようになっており、日本語の「あれ」と「これ」の違いや、ある程度意思の疎通が出来るようになっていた。
船が、操業を終え帰港中となりグァム島に向かい針路を取っていたある日のこと。
仕事をしている最中に、レンドンが小さい声で僕に話しかけてきた。
「ケイジ、ワタシコレ?ツギ?」と、親指を立てて首をかき切る仕草をした。
「私はクビですか?」と、僕に聞いてきたのだ。
僕は日本語で「私、わからない。船頭決める」と答えた。
レンドンは「ハイ」と言って、うつむいた。
その日の夜のワッチの時に、ワッチをしている僕の後ろを船頭が通りかかったので聞いてみた。
「船頭、レンドンは次の航海で乗せるの?」と。
すると船頭は「もう一人は使い物にならないが、アイツは結構使えるんじゃないか?お前どう思う」と僕に聞き返してきた。
レンドンの利点は“素直さ”だ。
素直が故、順応性が非常に高い。
言い換えれば、単純ということになるのだが・・・・。
「あいつは、使えるんじゃないですか。指示にも素直に従うし」と僕は答えた。
すると船頭は「そうか、お前もそう思うか」と頷きながら言った。
「ところで」と船頭が話を続けた。
「グァム島で水揚げをしないかと言う依頼が来てるんだが、お前どう思う?」と聞かれた。
「グァム島で水揚げできるの!?」と驚いて聞いた。
聞くと、グァム島にある日系の商社がマグロを買取、それを日本に空輸して日本の市場に卸すらしい。
僕は率直に「面白い!」と思った。
当時、僕の実家が経営し僕が乗るマグロ船は不振が続いていた。
2航海連続赤字が続き、死者を出す事故による出港停止状態が長く続いたことが大きく影響していた。
「グァムに水揚げをして3日で出港する。2航海に1度日本に帰港するというのはどうだ?」と、船頭は僕に聞いた。
僕は「航海の日数的には、今までと変わりないから問題ないと思うけど。問題は船員の外国での慣れない習慣とか、精神面での負担とかですね。でも面白いから、一度試しにやってみたらどうですか?」と答えた。
船頭は「そうか、やってみるか」と言った。
翌日、そのことが全船員に告げられた時、船員の反応は冷ややかだった。
日本という島国に生まれ、他人種との関わりをほとんど持たない彼らの心中は察するに余った。
船頭と兄がいないところで、僕に不満を漏らした。
しかし唯一、喜んでいる人がいた。
怪物君である。
彼の喜ぶ理由は唯一「外人とやれる!!」
当時、HIV感染症(エイズ)があまり知られていなかった頃だった。
僕は、HIV感染症の記事が載っている雑誌を怪物君に見せながら、内容を5倍くらいに盛って怪物君を脅した。
船員の不安と不満は、グァム島に近づくにつれて増しているように見えた。
僕や兄に愚痴をこぼす回数が増えていた。
そこで、僕は兄と船頭に提案をしみた。
日本の港に入港する際、入港金5万と仕込み金5万の合計10万円を、1.5倍の15万円にしサメのヒレ等を売った副収入に関しては、船頭は分配対象とせず船員で均等に分配するという案だ。
兄と船頭は、はじめ難色を示したが、船の士気の低さは仕事の質の低下に著しく影響を及ぼすし、航海日数が少なくなったと言うことは経費のコストカットができているはず。
コストカットできた経費を船員に分配するという考え方に変え、船員の士気を維持することの重要性を船頭と兄に説いた。
すると、まず兄がその案に同意をした。
同意した兄に続いて船頭が「まあいい、お前の好きにしろ」と言って船頭は同意をした。
数日後、船はグァム島に入港した。
亜熱帯地域特有の湿度が高く重い空気と容赦なく照りつける太陽、車のタイヤが焼けたような臭いと南国特有のノンビリとした雰囲気。
グァム島の港には商社の現地スタッフと、日本語通訳兼コーディネーターの韓国人のキムさんが出迎えに来ていた。
検疫と税関検査を受け、上陸許可が下りた。
接岸した場所は、グァム島のコマーシャルポートと言う場所だった。

港の向かい側には米軍の潜水艦基地があり、時折基地側から吹いてくる湿った風にのって油の臭いがした。
上陸許可が降りた船員達は、コマーシャルポート内の巨大な倉庫の中にある商社の事務所に招かれた。
そこで、簡単な歓迎セレモニーが開かれた。
商社のグァム支社長は、日系2世の小柄なデビット・イシマル(石丸)と言った。
自己紹介の時に「ディェイヴィット・イシマルです。どうぞよろしく」と、流暢な英語と日本語が混ざった感じで挨拶をした。
僕には「ディェイヴィット」が「デビット」と聞き取れず「ウェリット」に聞こえたので、それ以来僕は彼のことを「ウェリット社長」と呼んだ。
ウェリット社長が「貴方達は、グァムに新しいビジネスをもたらすパイオニアです。それを歓迎して今夜行われるグァム総領事官主催のパーティーがあります。今夜は私と一緒に出席しましょう!」と、えらいテンションの高さで言ったが、それを聞いた船員達のテンションは地に着く程低かった。
その船員達のテンションを低さと違和感を察知した船頭が突然
「船を代表してぇ~、こいつーが一人で出席しまぁぁす~」と
何故か英語なまりの日本語で僕を指さした。
僕は思わず「えぇっ!!」と声を上げたが
テンションの上がりまくっているウェリット社長は「Oh!あなた船頭さんの息子さんね!よろしくね!」と、僕にハグをしてきた。
僕は拒否する理由も見つからないし、パーティーと言う言葉の響きに興味があったので「まあ、行っても挨拶だけして帰ればいんだろ」と思い、言われるままパーティーに行くことにした。
夕方、僕は半パンとTシャツを着て船で待った。
少しするとウェリット社長の車が船の横に着き、その車でパーティー会場であるグァム総領事館の邸宅まで送ってもらった。
邸宅は小高い丘の上にあって、豪邸だった。
パーティーはアメリカの映画でよく見る、立食式のホームパーティーにで「おお!なんか映画みたい!」と思い、少しテンションが上がった。
総領事長らしいスラッと背の高い白人が、グラスをフォークで“チンチン”と鳴らし、パーティー出席者が彼に目を向けた。
どうやらパーティー開会の言葉的な挨拶をしているみたいだが、英語なので僕はさっぱりわからない。
その挨拶が終わり、ウェリット社長がパーティー参加者に僕を紹介した。
これまた、英語なので何を言っているのかさっぱりわからない。
パーティーの出席者何人かが僕に話しかけてきたが、何を言っているのかわからないので笑顔で会釈をするだけの僕。
そのうち、僕が英語が喋れないことを察したのか誰も話しかけてこなくなった。
一人ポツンとソファに腰をおろし、目の前で談笑するパーティーに参加した人達を眺めていた。
白人や黒人、現地のブラウンの肌をした人、いろんな肌の色をした人達が参加していて、その人達を眺めながら「アメリカって色んな人種の人がいるんだなぁ。マジ、映画みてぇだな」と思っていると、不意に「お腹すいてないの?」と日本語で話し掛けれられた。
声のする方を見ると、白髪でとても上品そうな日系人の顔をした女性が立っていた。
「あの、日本の方ですか?」と、僕はその人に聞き返した。
するとその人は、「そうよ、私は日本人よ。沖縄生まれの沖縄育ち」と流暢な日本語で答えた。
その人は「主人を紹介するわ、その後食事を運んであげる」と言いご主人を連れてきた。
さっきパーティーの開催の挨拶をした白人の男性で、やっぱりその人が総領事長だった。
改めて近くで見ると、総領事長は気品のある顔立ちをしていて紳士然とした人だった。
「総領事長の奥さんは日本人か」と、少し誇らしく感心した。
「ここはうるさくてのんびりお食事できないでしょ。プールサイドは涼しくてゆっくりお食事できるわよ、プールサイドにお食事を運んであげるわ」と、僕を中庭にあるプールのプールサイドに案内してくれた。

プールサイドにはパラソルとテーブルとイスが何脚かあり、僕はその中の一つに腰を降ろした。
奥さんが食事を運んで来てくれた。
僕が「ありがとうございます」とお礼を言うと「ごゆっくり」と言って、微笑み会釈をしあと奥さんはパーティーの中に姿を消した。
僕は運ばれてきた食事食べた後、タバコに火をつけてまん丸く夜をてらしている満月を眺めていた。
プールの中に光る電灯があり、時折吹いてくる風にプールに張られた水面をキラキラと揺らしていて、とても綺麗だった。
プールの先には、グァム島の海岸線のオレンジ色の街灯が揺れている。

昼間の照りつける太陽は去り、太平洋から吹き上げてくる潮の香りが混ざった夜風はとても心地よかった。
僕は、タバコをくわえたまま夜空を見上げた。
夜空は街灯のオレンジ色が映り込んでいて、海の上にに比べると星はあまり見えなかった。
タバコをくゆらせながらグァム島を眺めている僕に突然「ごきげんよう!」と、後ろから日本語で女性が声を掛けた。
振り返るとそこには金色のロングヘアで少し日焼けした肌、ハッキリとした均整のとれた顔で、スラリと背の高い女性が立っていた。

僕は、ひと時その人に見とれてしまった。
「こんな綺麗な人、世の中にいるんだ・・・」と、心でつぶやいていた。
その人は「ごきげんようじゃないわね、こんばんはね」と言って笑った。
僕は「そうだね」と言うのがやっとだった。
彼女は「私、ジュリア。よろしく」と言って、握手をする仕草で右手を差し出した。
僕は「ケイジ。よろしく」と言って、握手を交わした。
その人の手は、柔らかくて少し暖かかった。
ジュリアは僕の左斜め前のプールサイドに腰をおろし、足だけをプールの水に浸していた。
「パーティー、楽しくないの?」と、プールを見つめたまま僕に聞いた。
「俺、英語喋れないから」と僕が答えると「そうなんだ、じゃあ楽しめないよね。英語、覚えなきゃだね!」と、僕を振り返り微笑みながら言った。
ジュリアはプールに浸した足をゆっくりと動かしている。
その足の動きでプールには波紋ができ、プールを照らしている明かりが波紋に反射してジュリアの綺麗な横顔に映っていてキラキラと輝いていた。
僕は輝く彼女の横顔に見とれながら「大人っぽい人だなぁ」と思った。
「君、何歳なの?」と、僕はジュリアに聞いた。
「23歳だよ」と、ジュリアは答えた。
“やっぱり年上か”と思った。
「綺麗だね」と僕が言うと、ジュリアは僕に向かって振り向き笑いながら「Thanks」と言ってウィンクをした。
彼女は「ねぇ、足を水につけると気持ちいいよ」と僕に言った。
僕はジュリアに言われるままに、彼女の横に腰を下ろしプールに足をつけた。
確かに気持ちがいい。
「今日入港した漁船の人なんでしょ。あなた、何歳なの?」とジュリア。
「俺、19歳。」
「へぇ!19歳なの!大学に行こうと思わなかったの?」
「高校を卒業したら、船に乗るって決めてたから」とプールを見つめたまま言った。
ジュリアが綺麗すぎて、彼女の顔を見ることができなかった。
僕の顔を、ジュリアが見つめているのがわかった。
僕はジュリアを見て「ん?」と言った。
「決めてたって、あなたまだ19歳だよね。いつから決めてたの?」と、不思議だという感じで僕に聞いた。
「覚えてない。子供頃、親父カッコいいなぁって思った時だと思う」と答えると。
「決めてたからって、なりたいものになれるものなの?」と、また僕に聞いた。
僕には、その問い掛けが不思議でならなかった。
そういう風に、自分の仕事を考えた事が無かった。
「よくわかんないけど。なれるって思ってたし。そういう家に産まれたから」と僕が言うと「それ、すごい事だと思うよ」と彼女は言った。
僕は、ジュリアのその言葉がすごく嬉しかった。
「ごめんなさい、嘘ついてた。私、19歳。あなたと同じ歳よ」と言って、彼女は声を出して笑った。
笑っている彼女の顔を見ると、確かに幼さが残っているように思えたが綺麗さは揺るぎなかった。
「ねえ、グァムは初めて?」とジュリア。
「うん、初めてだよ」と僕は答えた。
「じゃあ、仕事だけじゃなく遊んだりもしなきゃ!船はどこにあるの?」
「コマーシャルポートってところにある」
「遠い!あの辺り、何もないでしょ!」
確かに車でくる途中、海と基地らしい建物しか見えなかったなと思った。
「英語覚えたくない?」と、ジュリアは聞いた。
中学生の時、矢沢永吉のRockに出会い、その後ビートルズやローリングストーンズ、クリームやブルース・スプリングスティーン等を聞き漁った。
その頃から「英語の歌詞がわかったら、もっと楽しいだろうな」と思っていた。
「覚えたいよ。歌の歌詞がわかるとすごく楽しいだろうなって思う」と僕が答えると
「私が英語教えてあげる!そのかわり、あなたは私に日本の事を教えて」と彼女は言った。
「君は十分日本語が上手だよ、僕より綺麗な日本語を喋ってる」と僕が言うと。
「確かにあなたの日本語は、ちょっとアクセントが変だよね」と笑いながら言って「言葉じゃないの。日本の習慣とか日本人の考え方とかが知りたいの。私、半分日本人だし日本の文化に凄く興味があるの」と言った。
その時、ジュリアがハーフであることを知った。
こんな綺麗な人と友達になれるのなら、断る理由などどこにもない。
「いいよ」と、僕は二つ返事で答えた。
「うん。よろしくね!」と、彼女はまた右手を差し出した。
僕が握手をしようと、彼女の右手を握ると
「はぁ~、ダメね」と、ため息交じりに言い僕を睨むような顔で
「あのね、こう言うときはね。そっと手にキスするものよ」と言ったあと、微笑んだ。
“照れ臭い!”と思い、ジュリアの柔らかな手を離して「んなこと、できないよ」と僕が言うと「照れなくていいんだよ」と彼女は微笑みながら言った。
二人でプールサイドに腰掛け、僕の子供の頃のことや父や兄や家族の事。
ジュリアはアメリカ人と日本人のハーフで、ここの家の娘であること。
さっき僕をプールサイドに案内してくれた人がお母さんで総領事長がお父さんであること。
東京に3年位住んだことがあることや、今はグァムの大学に行っている事。
時間が経つのも忘れて、夢中になって話した。
どのくらい時が経ったのだろう。
話をしているうちに、彼女に対する僕の心の壁のようなものはいつしか無くなっていた。
すると「ケイジさん、ディヴィットさんがそろそろお帰りになるそうよ」と、二人の会話を遮った。
振り返るとジュリアのお母さんが立っていた。
僕は「はい」と答えて、立ちあがるとジュリアもそれに続いた。
玄関先に行くと、ジュリアのお父さんである総領事長やパーティーに参加した人達が僕を見送りに出ていた。
ウェリット社長の車に乗り込もうとした時、ジュリアが「みんなに、お礼の挨拶して」と僕に言った。
英語が喋れない僕が戸惑っていると「日本語でいいの」とジュリアは言った。
僕は日本語で「本日は、素敵なパーティーにお招き頂きありがとうございました!」と、大きな声で言うと、ジュリアが僕のゼスチャーを真似ながらそれを通訳してくれた。
見送りの人達から僕に、拍手と笑いが起こった。
僕が車に乗り込もうとした時「明日、学校が終わったら船に迎えにいく」とジュリアは僕に耳打ちをした。
僕は「うん」と言ったが、何時にどこで等と細かい事は約束せず車のドアを閉じた。
帰りの車の中で、車窓から流れるオレンジ色の街頭と暗い海を眺めていた。
ジュリアの笑顔が瞼の裏側に焼き付いていて離れない。
それを察したのか「彼女、いい子でしょ。すごく人気があるんだよ」と、ウェリット社長が言った。
「綺麗ですよね。人気があるのはわかる気がします」と僕が答えると
「でもね、一つ君に忠告しておこう。現地の女の子に手を出すなよ。手を出すなら、それなりの覚悟が必要だよ」と、それまで笑顔で話してたウェリット社長は真面目な顔をして僕に言った。
僕は「わかりました」と答え、また外を見た。
船に戻ると、船内は静まりかえっていた。水揚げを2時に控えているため、みんな寝ているようだ。
僕はシャワーを浴びた。
入港時、清水は使い放題だ。
無くなれば、補給すれば良い。
シャワーを浴び終えると、寝台に入り目を閉じた。
すでにジュリアのことで頭の中は一杯で、目を閉じると彼女の笑顔が浮かんでくる。
1時30分、水揚げスタンバイのベルで目覚めた。
陸にはマグロを巻き上げるために、クレーン車が用意されていたて短尺状にしてクレーンにマグロが釣り上げられていく。

船からクレーンで巻きあげられたマグロは、氷を張った海水が入っている巨大な桶に移され、その桶をフォークリフトで倉庫内に運ぶ。
倉庫の中では一本一本マグロの重さが図られ、マグロの大きさに応じた段ボール箱に納められていく。日本との水揚げの方法が違ったのと、現地スタッフは初めて水揚げの作業をする人がほとんどだったこともあり、水揚げにはすごく時間がかかった。
水揚げが終わった時、時計はすでに10時を廻っていた。
日本での水揚げは、大体約4時間で終わる。
その時は、通常の倍以上の時間を要した。
夜が明け切ると太陽は容赦なく照りつけていて、魚倉の掃除をして片付け等の全ての作業が終わると、時計は12時を過ぎていた。
水揚げが終わり、船頭から船員達にに入港金と仕込み金として$1,000が船員に支給された。
当時の円に換算すると約16万になる。
僕は「$紙幣って、子供銀行のお金みたいだ」と思った。
コマーシャルポートからグァム市街地までは車で30分程かかる。
仕込みに行くため、コーディネーター兼通訳としてキムさんが付き添ってくれることになった。
キムさんのライトバンに乗り込み、仕込みに行った。
「ギブソンズ」というスーパーマーケットに着き、1時間半後にキムさんのライトバンを駐車した場所で待ち合わせになり、船員達は各自が自由にギブソンズで買い物をした。
僕は兄と怪物君と三人で仕込みの買い出しをしていて、CD売り場を見つけた。
もちろんCDのタイトルは全て英語で書かれているため、良くわからない。
BEST HIT書かれたタイトルに、バンド名等が書かれているが読めたのは「STING」くらいだった。
CD一枚の値段は$12くらいで、僕は「物は試し」と、BEST HITのNo.1~10までの10枚とジャケットがカッコ良くて気になった一枚を買った。
その他、食料や衣類を買い込み、仕込みの買出しを済ませて船に戻った。
船に戻ってもすることが無く、前日からあまり寝てなかったこともあり寝台で横になるとすぐに眠りに落ちた。
眠っていると「ケイジ。フレンド、アル」とレンドンが僕を起こした。
「フレンド??」と僕が聞き返すと、レンドンは「ハイ」と答えた。
寝ぼけた感じで外に出てみると、白いピックアップトラックの横にサングラスをかけたジュリアが立っていた。
ジュリアは僕を見つけると「Hi!」と言って、僕に向かって手を振った。
「ほんとに来たのか!?」と僕が聞くと、僕を指差し「そう言うの良くない、約束したよ!」と、彼女は少し怒った顔で言った。
「ちょっと待ってて、用意してくる」と言って、急いで僕は船員室に戻りTシャツとジーンズに着替えた。
昨夜の夜より、昼間に見るジュリアは綺麗だった。
気分が高まった。
階段を駆け上がり船尾甲板でると、レンドンと怪物君がいて、怪物君がレンドンに悪い日本語を教えていた。
怪物君は自分の股間のあたりを指差しながら「オンナ。ココ。オ○○コ。」とレンドンに教えていて、レンドンはニヤニヤした顔で「ココ。オ○○コ」と、怪物君が教える日本語を復唱していた。
最低な奴らだ。
怪物君はレンドンが復唱すると「ギャハハハ」と笑っている。
お前がギャハハハだわ。
二人に向かって「俺、友達と遊びに行ってくる」と言うと「あの美人、誰だ!?」と怪物くんが僕に聞いた。
「昨日知り合った友達だよ」と言いながら、僕は船から飛び降りた。
二人には目を向けず、ジュリアの車に向かって歩いてくと「この、スケコマシ!」と、背後から怪物君の罵声が聞こえたが完全に無視した。
車まで来た僕に「乗って」と言って、ジュリアは車の運転席に乗り込んだ。
車内はすごく良い香りしていた。
ジュリアは「夕暮れまでには、もう少し時間があるから。ちょっとドライブしよう」と言って車を発進させた。
僕は、不思議でならなかった
僕は改めて「本当に来たんだね。でも、なんで?」と聞いた。
僕はただのFishermanで、彼女は道を歩けば誰もが振り返るほど容姿端麗。
パーフェクトな美人だ。
どこから見ても、俺とは釣り合いが取れないだろうと思っていた。
質問した僕に対してジュリアは「なんでだろうね?」と、質問に質問で返して誤摩化したので僕はそれ以上は聞くのをやめた。
車は小高い丘を上りジャングルを切り開いたような道を進み、いきなりジャングルの道から海岸線出て、凹凸のある曲がりくねった道を進んで行った。
道の途中の所々に、民家らしい10戸程度の集落が点在していた。
ジュリアは鼻歌を歌いながら車を走らせ続け、ほどなくして海岸沿いの小さな駐車場に車を止め「着いたよ」と僕に言って、ジュリアは車のドアを開けて降りたので僕もそれに続いた。
車から降りると、とても穏やかで涼しい風が吹いていた。
駐車場から十メートル程歩いた先に、小さな砂浜があった。
太陽は、それまで照らし続けた自身を祝福するかのように海を真っ赤に染め水平線に沈み行こうとしていた。
小さな砂浜に降る階段に着くと「座ろう」と、ジュリアは僕に言った。
僕は「うん」と言って、ジュリアに並んで座った。
タバコに火を付けて、沈む行く夕日を眺めていた。

“こんな穏やかで素敵な夕日を見たの、何年振りだろう?”と思った。
エンジン音のしない海は不思議な感じで、さざ波と緩やかな風の音以外、何も聞こえない。
昨夜、プールサイドでジュリアと語り合った時、ジュリアは僕に聞いた。
「海、好きなの?」
僕は素直に「好きだ」と答えられなかった。
「どうだろう?職場だから」と、笑って誤摩化した。
物心ついたときから、海は僕にとって職場に等しかった。
祖父に連れられ漁に出る、海を見る時には無意識に潮目を読む癖がついていて「今日は潮が悪いから良い漁はできないな」などを考えるようになっていて、海で遊んだ記憶は小学校に入学する前、近所のお兄ちゃん達に連れられて行った浜辺で遊んだ記憶しかない。
海に囲まれて育ったのに。
沈み行く夕日が欠片になり、辺りに夜の帳が下り始めた頃「ねぇ、静かな海を思い出した?」と、彼女は僕に聞いた。
僕は海を見つめたまま「ああ、思い出したよ」と答えた。
「さっき聞いたよね。なんで俺かって」と彼女。
僕は、また「ああ」と答えた。
「あなたと話したときに感じたの、海のような人だなって。包み込まれそうだなって。そういう感じがしたの」と彼女は言い「穏やかなときはこんなに優しいの」と続けて言った。
そういう風に、僕のことを表現する人と出会ったのは生まれて初めてだった。
僕の心に、恥ずかしさと嬉しさとが交叉し、そしてなんとなく切なかった。
「なあ、抱きしめてもいいか?」と、唐突にジュリアに聞いた。
彼女は海を見つめたまま、僕の顔を見ることなく「聞かなくいいのに」と言って僕に寄り添った。

僕は彼女の肩を抱き、夕日が完全に消えて行くのを何も言わず見つめていた。
その夕暮れは、どんな映画よりも幻想的で、且つエキサイティングだった。
途中ジュリアは、僕の気持ちを察したかのように「私に気を使わなくていいからね、気が済むまで眺めていようよ」と言った。
夕日が完全に沈むまで、僕は彼女の肩を抱いたまま無言で海を見つめていた。
夕日が沈み、辺りが夜に包まれるとジュリアは「お腹すいたよね」と言った。
ジュリアのお勧めの小さなチャモロ料理レストランに行き、食事をしながらいろんな話をした。
あっという間に時間が過ぎた。
帰りも車で僕を船まで送ってくれて、帰りの途中で「明日、出港するから」と僕が言うと、ジュリアは「うん」と言った。
船が接岸しているコマーシャルポートは、グァム島の国際港でセキュリティゲートがあり、セキュリティーゲートから船までは少し距離ある。
セキュリティゲートでチェックを受けて、車はゲートを抜け船の前に車は止まった。
止まった車の中で無言の時間が流れた時に「本当に鈍感!」と、ジュリアは少し怒った感じで言った。
ジュリアが、何を指して言ったのかは理解できた。
映画のワンシーンの様に、臭いセリフを言ってキスに持ち込むパターン。
でも、照れ屋の僕は「俺、日本人だからさ」と言うのが精一杯だった。
「Cool!そういう日本的な事を素直に言うところが良いよ」と言ったあと「でも、女心も理解してね」と言った。
僕は「またグァムに来るから。その時は、また会ってほしい」と僕が言うと、彼女は「喜んで」と笑った。
彼女の笑顔は、品のない街頭に染まっていて良く見えなかった。
翌日、船はグァム島を出港した。
ジュリアは見送りには来なかったが、ウェリット社長がジュリアからのメッセージカードを僕に渡した。
メッセージカードに「Good luck!J boy!」と書かれてあった。
つづく

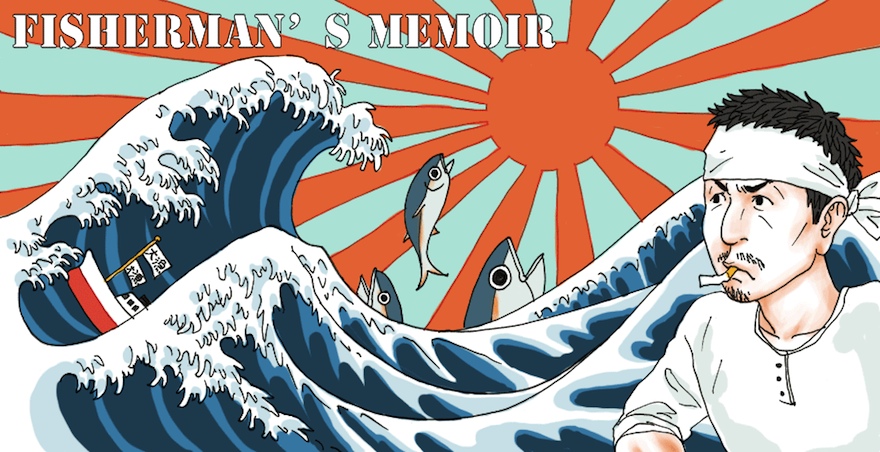

コメント